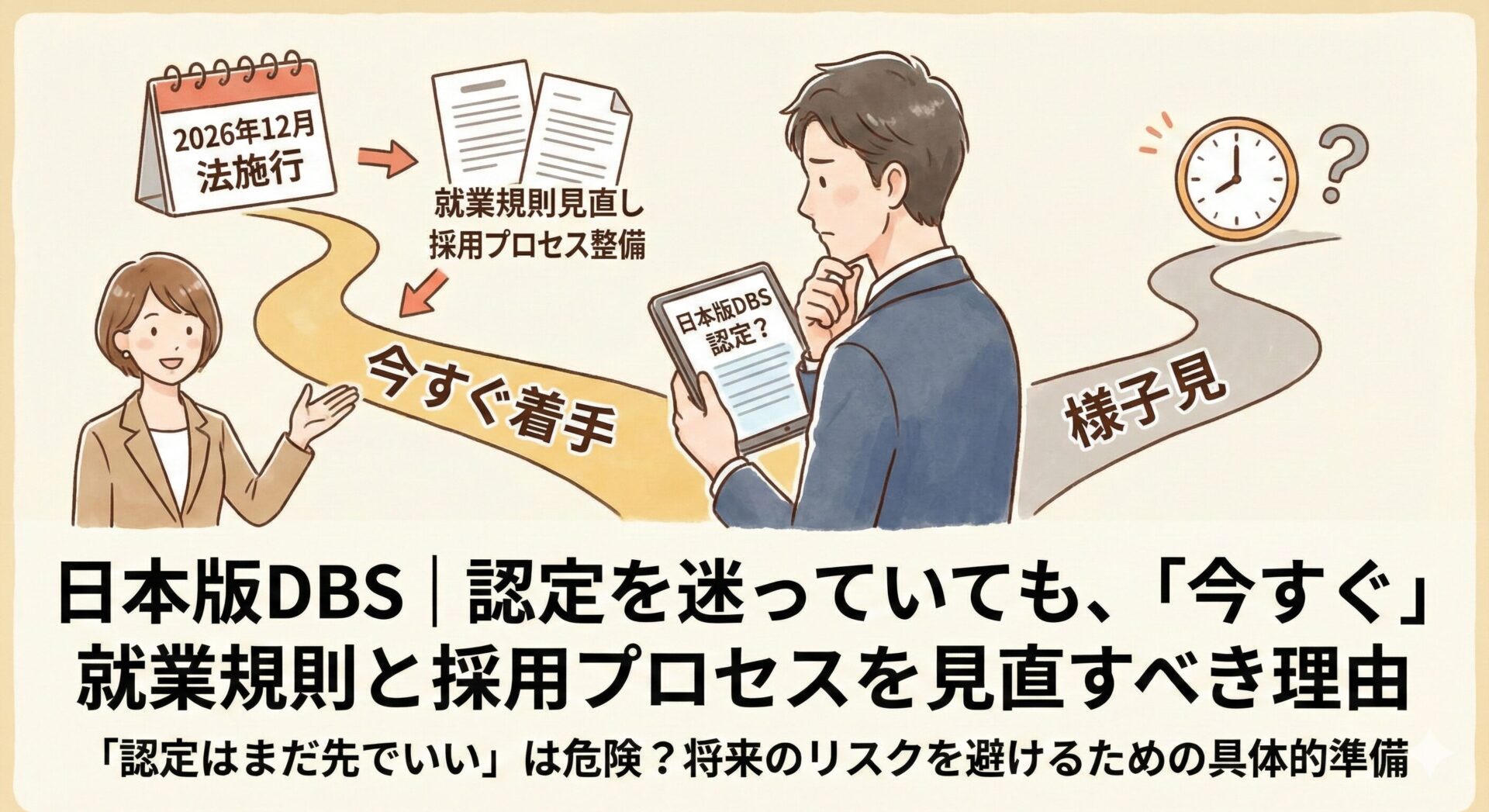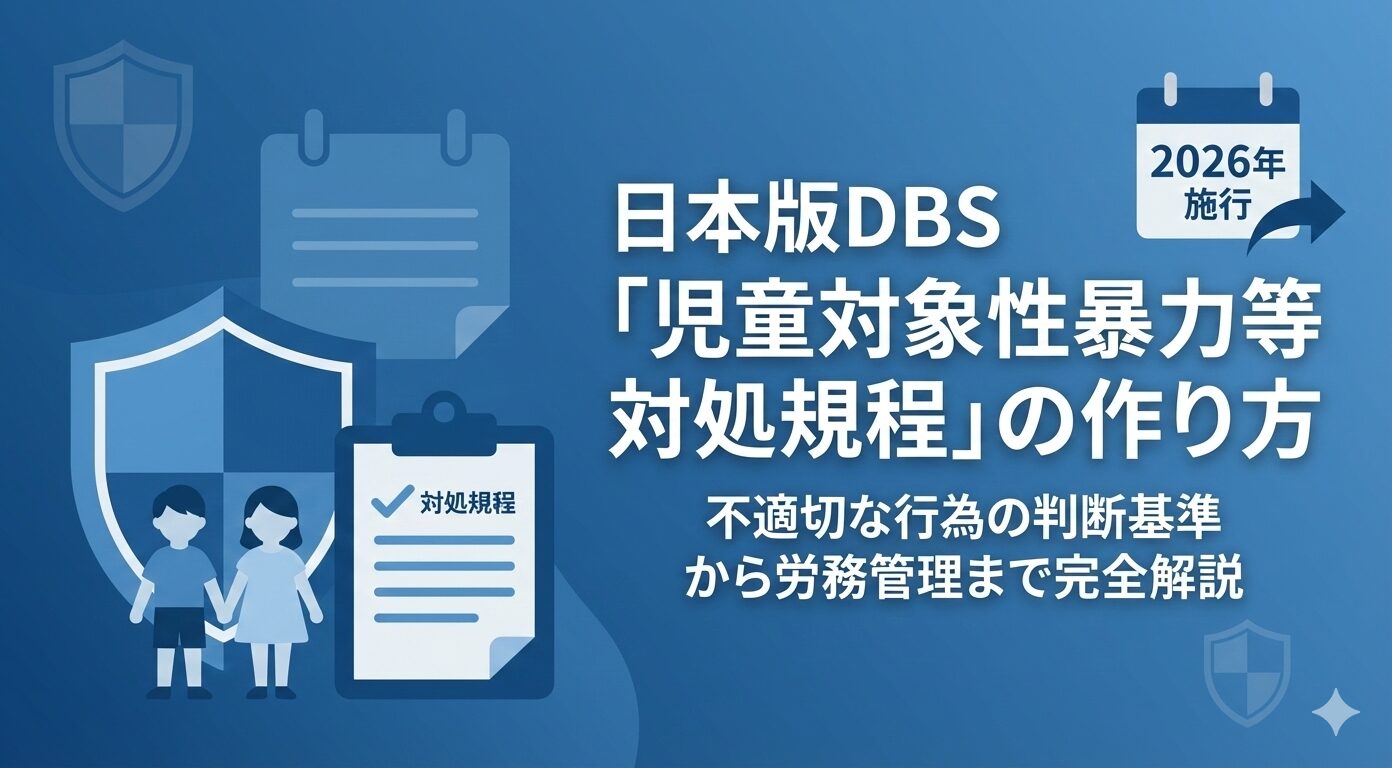うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説

「この前、日本版DBSの記事を読んだけど、結局うちの教室は対象になるの?」
「認定は“任意”って書いてあったけど、本当に何もしなくて大丈夫?」
前回の日本版DBSの概要記事に引き続き、今回はこの新しい法律の「対象範囲」にグッと焦点を当てて、「どんな事業が対象になるのか」「どこまでが義務で、どこからが認定なのか」を、日本一わかりやすく解説します!
あなたの事業がどこに当てはまるのか、この記事を読みながら一緒にチェックしていきましょう。
まずはおさらい!「義務」と「認定」の2つのルート
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、子どもと関わる事業者を、その性質によって2つのグループに分けています。
- ① 義務の対象(学校設置者など) 法律が施行されたら、自動的に、必ずDBSの仕組みを導入しなければならない事業者です。
- ② 認定の対象(民間教育保育など) 法律上の義務はありませんが、自ら手を挙げて国の審査を受け、「認定」されることでDBSの仕組みを導入できる事業者です。
あなたの事業がどちらのルートに当てはまるのか、具体的に見ていきましょう。
ルート①:義務の対象となる事業者
こちらは、主に国や自治体からの「認可」や「指定」を受けて運営されている施設が中心です。公立・私立は問いません。
- 学校関係:幼稚園、小学校、中学校、高校など
- 認定こども園
- 児童福祉施設:認可保育所、児童養護施設、児童館、放課後等デイサービスなど
もし、事業が上記のいずれかに該当する場合は、2026年の施行に向けてDBS導入の準備が必須となります。
ルート②:認定の対象となる事業者【※ほとんどの民間事業はココ!】
学習塾、スイミングスクール、ピアノ教室、サッカークラブ、ベビーシッターなど、いわゆる「認可外」の民間事業のほとんどは、こちらの「認定」の対象となります。
「うちは認定の対象なんだ!じゃあ、具体的にどんな事業が当てはまるの?」
特に、学習塾やスポーツクラブといった「民間教育事業」が認定を受けるには、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。一つずつ、丁寧に確認していきましょう。
【重要】民間教育事業が認定を受けるための「5つの条件」
条件①:子どもに何かを「教える」事業であること
子どもたちに知識や技術(技芸)を授けることが事業の目的である必要があります。 学習塾のように勉強を教える、ピアノ教室で演奏を教える、サッカースクールで技術を教える、といった事業がこれに当たります。
逆に公園のプレイパークのように場所を提供するだけの事業は、この条件には当てはまりません。あくまで「教育」がメインであることが必要です。
条件②:「6か月以上」継続して通えるコースがあること
これは、事業の継続性を見るための条件です。 夏休みだけの短期水泳教室や、1日だけのプログラミング体験会といった単発のイベントだけを行っている事業は対象外です。
月謝制の学習塾や、年間カリキュラムのある音楽教室のように、同じ子どもが継続的に(少なくとも半年にわたって)通うことのできるコースや仕組みがあることが求められます。これは、指導者と子どもの間に継続的な関係性が生まれやすい事業を対象とするためです。
条件③:「対面」で直接指導していること
これは文字通り、先生と生徒が直接顔を合わせて指導する形態である、ということです。 Zoomなどを使ったオンライン授業だけで完結している事業は、この法律の認定対象にはなりません。あくまで、物理的に同じ空間で指導が行われることが前提となります。
条件④:事業者が「場所を用意」して指導していること
これは、指導する場所の管理責任がどこにあるか、という視点の条件です。 生徒の自宅に訪問する「家庭教師」は、原則としてこの条件を満たさないため対象外となります。なぜなら、その場所(生徒の自宅)を管理しているのは事業者ではなく、保護者だからです。
この法律が対象とするのは、塾の教室、音楽スタジオ、スイミングスクールのプール、公民館の一室など、事業者側がレッスン場所として用意・管理している空間です。事業者の管理下にある場所は、保護者の目が行き届きにくく「閉鎖的な空間」になりやすいため、特に注意が必要だと考えられているのです。
条件⑤:指導者の人数が「合計3人以上」であること
これは、事業の規模を見るための条件です。ここでいう「指導者」とは、正社員だけでなく、パート、アルバ’イト、業務委託の講師など、実際に子どもに教えているすべての人を含みます。
例えば、経営者である塾長1人と、アルバイト講師2人で運営している塾は、合計3人なのでこの条件を満たします。個人事業主の先生が1人だけで運営しているピアノ教室などは、対象外となります。 (※この人数は、今後、国の政令によって変更される可能性もあります。)
【注意】 この「3人以上」は、あくまで民間教育事業が認定対象となるための条件です。認定を受けるためには、これとは別に「情報管理体制として2人以上」という要件もあります。詳しくは次のセクションで解説します。
【補足】認定には「2種類の人数要件」がある
民間教育事業者が認定を受けるためには、実は2種類の人数要件をクリアする必要があります。
この2つは混同されやすいので、ここで整理しておきましょう。
要件①:事業の定義としての「3人以上」
先ほど条件⑤で説明したとおり、学習塾やスポーツクラブなどが「民間教育事業」として認定の対象になるには、講師・インストラクター等が3人以上いることが前提です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 技芸又は知識の教授を行う者(講師、インストラクター等) |
| 人数 | 3人以上 |
| 雇用形態 | 問わない(正社員、パート、派遣、ボランティアすべて含む) |
要件②:情報管理体制としての「2人以上」
認定を受けるための基準として、情報管理の責任者を含めて従事者が2人以上であることも求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 犯罪事実確認記録を取り扱う従事者 |
| 人数 | 2人以上(責任者を含む) |
これは情報管理責任者が一人、犯罪事実確認の情報を取り扱わない従事者が1人でもOKです。また、子どもたちと接することのない事務員の方も対象となります。
まとめ:両方を満たさないと認定は受けられない
| 要件 | 内容 | 満たさない場合 |
|---|---|---|
| 3人以上 | 子どもに教える人数 | そもそも認定の対象外 |
| 2人以上 | 情報管理体制の人数 | 認定基準を満たせない |
つまり、「教える人が3人以上」いることが大前提となり、その上で「情報管理を2人以上でチェックできる体制」を整える必要があります。
例えば、子どもに関わらない経営者と事務員1人、バイト講師3人なら認定を受けられます。(=情報管理規程もクリア)
【ポイント】 学校や認可保育所などの法定事業者(義務対象)には、この「3人以上」の要件は適用されません。
うちは要件を満たしているの。。。?とご心配になったらお気軽にお問い合わせください。
誰の犯罪歴を確認する?対象となる「人」の特定方法
あなたの事業所が「義務」または「認定」の対象だと分かったら、次にクリアすべき課題は「どのスタッフの性犯罪歴を確認すべきか?」という点です。これを正確に特定することが、法律を遵守する上で極めて重要になります。
ポイントは、役職名(例:教室長、正社員)や雇用形態(例:アルバ-イト、業務委託)で一括りに判断するのではない、という点です。確認が必要かどうかは、その人が日常的に担当している「仕事のやり方」や「子どもとの関わり方」で決まります。
あなたのスタッフは大丈夫?対象者かを判断する『3つの視点』
法律では、子どもとの関係性において、以下の3つの視点すべてに当てはまる業務を「対象業務」としています。あなたの事業所のスタッフ一人ひとりの普段の働き方を、この3つの視点に照らし合わせてみてください。
視点①:子どもに対して「先生」や「コーチ」といった優位な立場か?(支配性)
これは、スタッフと子どもの間に「指導する側とされる側」というパワーバランスがあるか、ということです。
子どもからすれば、先生やコーチの言うことは「聞かなければいけない」と感じやすいものです。この力関係が、不適切な行為への抵抗を難しくさせる可能性があるため、重要な視点とされています。
- 【該当する可能性が高い例】
- 教科やスポーツの技術を教える講師、コーチ
- 活動の指示を出すキャンプのリーダー
- 送迎ルートなどを管理・指示する送迎担当者
視点②:同じ子どもと繰り返し接し、顔なじみの関係になるか?(継続性)
これは、どの程度の接触頻度があるか、という視点です。
一度きりのイベントで会うゲスト講師とは違い、毎週同じ曜日に顔を合わせる先生には、子どもも親近感や信頼を寄せます。この「顔なじみ」の関係性が悪用されることを防ぐためのチェックポイントです。
- 【該当する可能性が高い例】
- 月謝制のクラスを担当し、毎週同じ生徒を教える講師
- ほぼ毎日、同じ園児の送迎を担当するバスの運転手
- 定期的に相談に乗るスクールカウンセラー
視点③:他の大人の目がない「1対1」の状況になりうるか?(閉鎖性)
これは、周囲から見えない、あるいは見えにくい状況で子どもと二人きりになる機会があるか、という視点です。
例えば、ガラス張りのオープンな空間での集団レッスンと、防音扉のある個室でのマンツーマンレッスンでは、状況が全く異なります。保護者や他のスタッフの目が行き届かない「密室」は、性暴力のリスクが最も高まる環境の一つです。
- 【該当する可能性が高い例】
- 個室でのマンツーマンレッスンを担当する講師
- 生徒一人だけを車に乗せて送迎することがある運転手
- 別室で進路相談やカウンセリングを行うスタッフ
以上の3つの視点を踏まえ、あなたの事業所の全スタッフの業務内容を一人ひとり具体的に洗い出し、「対象者リスト」を作成することが、日本版DBS対応の第一歩となります。
【行政書士から一言】 > 事業者さんの運営によって、この場合は当てはまるのか、この人は除外していいのか…悩むケースが多いかと思います。そんな時は、私たちにご相談ください。
「認定」は事業の未来を守るための“信頼の証”
「うちの事業は認定の対象範囲に入っていることが分かった。でも、手続きも大変そうだし、本当に認定を受けるべきだろうか…」 そうお悩みかもしれません。
しかし、この「認定」を受けることは、単なる法対応以上の、事業の未来を守るための大きな価値を持ちます。
メリット1:保護者から「選ばれる」理由になる
認定を受けると、国が定めた「認定マーク」をホームページやパンフレットに掲載できます。 これは、「私たちは、国の厳しい基準をクリアし、子どもたちの安全に真剣に取り組んでいます」という何よりの証明です。習い事選びで安全性を重視する保護者にとって、このマークは絶大な安心材料となり、競合との差別化につながります。
メリット2:万が一の時の「法的リスク」を低減する
認定を受けるためには、性暴力防止に関する社内ルールを整備することが必須です。これは、万が一トラブルが発生した際に「事業者としてやるべき対策を講じていた」という証拠となり、事業者自身を守る盾にもなります。
認定取得は、専門家との二人三脚で
認定を受けるには、国の基準に沿った体制づくりや、複雑な申請書類の作成が不可欠です。

事業運営で多忙な経営者様が、これら全てを独力で進めるのは、計り知れない負担となります。
【お任せください】 私達、許認可申請のプロである行政書士は、こうした複雑な認定手続きの専門家です。また、社会保険労務士は労務のプロとして認定に必要な労務環境の整備が可能です。
国の求める基準をクリアするための体制づくりのアドバイスから、必要な書類の作成、そして申請の代行まで、ワンストップでサポートいたします。
子どもたちの安全と、あなたの事業の信頼を守るための「認定」という選択。まずはお気軽にご相談ください。